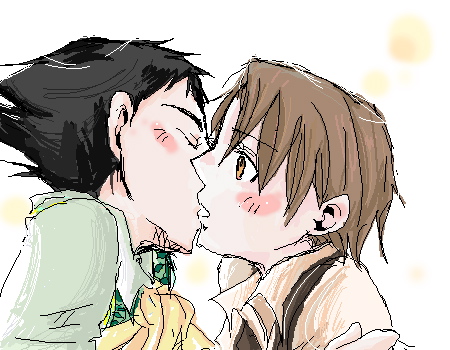|
CHAPTER4 創立祭
創立祭3日前。学校中が準備でごった返している。
ツバサたちも、その例に洩れることなく慌ただしく過ごしていた。
「衣装合わせやるから、ツバサとミサキ、こっち来てくれるかな。」
どんなに慌ただしい中でも、委員長のミスギは相変わらず端正な面持ちで紳士的である。
「ミスギだってきれいなんだからさぁ、ミスギがロザリーやれば良かったんだよ。」
女物の衣装を用意され、ミサキは今さらながら愚痴をこぼした。
「しょうがないよ、ツバサのご指名だったんだから。」
「大丈夫!ミサキ、絶対女の子に見えちゃうから!」
ツバサが妙にうきうきしながら言うのを見て、ミサキは「そういうことじゃないんだけど…」と、溜息をついた。
その言葉通り、良家の子女らしいドレスを着たミサキは、どう見ても可愛らしい少女に見えた。
それ以上にクラスメイトが盛り上がったのは、ミサキが羊番の衣装に変えた時である。
「どうだろう!?観客は男って思うかな、女って思うかな!?」
「男子校だから男のはずなんだけど…って、絶対迷うよな!」
「アンケート用紙配って観客にあててもらうとかは!?」
皆、口々に勝手なことを言って盛り上がっている。ミサキは増々深い溜息をついた。
ツバサはそれを見て、ニコニコと上機嫌だった。
いよいよ当日。
今日は、普段は閉じられている学校の正門が開き、桟橋を渡って大勢の客が来る。
生徒達も皆、浮き足立っていた。
「ツバサー!」
「母さん!俺の劇は午後だよ!もう来たの!?」
「いいじゃない。ツバサが、この学校の景色はきれいだって手紙で教えてくれたでしょ。だからゆっくり見ようと思って…」
「ツバサ、君の、お母さん?」
横にいたミサキが話に入ってきた。
「あら、あなたがミサキね?まあ、本当に可愛らしい子!ツバサから…」
「もう、いいよ。母さん、ド−ナツ屋が名物だから食べてきな。俺たち、忙しいから…」
「まあ、冷たいわねー。じゃあね、ミサキ。今度、是非うちにも遊びにいらっしゃいな。」
ツバサの母は、ツバサによく似た、明るい、くるくるとよく表情の変わる可愛らしい人だった。
「素敵なお母さんだね。羨ましいな。」
「素敵っていうか、賑やかっていうか、うるさいっていうか…。」
ツバサは少し恥ずかしそうに言った。
ああいう人と生活をしたら、ツバサみたいに素直で、いつも明るい方を向いていられるのだろうかと、ミサキは心の中で思った。
「ミサキ!」
ゲンゾーの声で呼ばれ、振り向くと、彼とそっくりな父親といた。
(悪いな、またお前の顔が見たいってしつこいから…)
ゲンゾーはすまなそうに、ミサキの耳もとに囁いた。
「ミサキ…。また会えて、嬉しいよ。その…お母さんは、お元気なのだろうか?」
「ごめんなさい、僕、本当に知らないんです。母さんのこと。あれから一回も会っていないので。」
ミサキは、事務的に答えた。
ゲンゾーの父は「そうだよね、すまなかったね。」と残念そうに微笑み、それを見たミサキはなんだか気の毒な気がした。
この人は、母とどういう思い出があるのだろう。
きっと、自分よりは沢山、母のことを知っているのだろう。
あの、朽ちてしまったブランコを思い出し、切ない気持ちが込み上げてきたミサキは、素っ気無く「じゃあ」とだけ言い残し、急いでその場を立ち去った。
「ミサキ!劇、頑張れよ!俺、ちゃんと見に行くからな!」
ゲンゾーは敢えて、とても明るい声で言った。
ミサキは振り向き、小さく笑うと、手を振って応えた。
「ああ…あの顔、彼女にそっくりだ…。」
ゲンゾーの父が懐かしそうに呟いた。
「思い出を重ねられるなんて、いい迷惑だと思うぞ。」
父のミサキに対する言動を戒めるつもりでゲンゾーは言った。
父親は、寂しそうに笑っただけだった。
さすがに、学校のアイドルのミサキ、今や下級生から熱烈な支持を受けるツバサが主演とあって、『お気に召すまま』の舞台となる講堂は一杯の人だった。
「うわ〜。すごい人ぉ…。」
舞台の袖からこっそり観客席を覗き、ツバサが驚きの声をあげた。
「ツバサ、これが、ミサキの人気の威力だ。すげえだろ。」マツヤマが、何故か自慢げに言った。
「ツバサ、全員、ジャガイモだと思え。」イシザキが言う。
ツバサは神妙な面持ちで頷いた。ミサキは慣れっこなのか、そんなツバサを見てクスクスと笑っていた。
開演。
緊張するなどと言っていたわりに、さすがツバサは堂々たる演技で、下級生たちを魅了していた。
いよいよヤマ場。オーランドが、それこそがロザリー本人だとは知らずに、羊飼いの少年相手にロザリーへの告白の練習をするシーンがきた。
熱心に告白の練習をする、ツバサ扮するオーランドの姿に、観客たちはクスクスと笑っている。
舞台の袖で、ミスギは満足そうに頷いた。
その時だった。
オーランドが、羊飼いの少年にキスをしたのである。
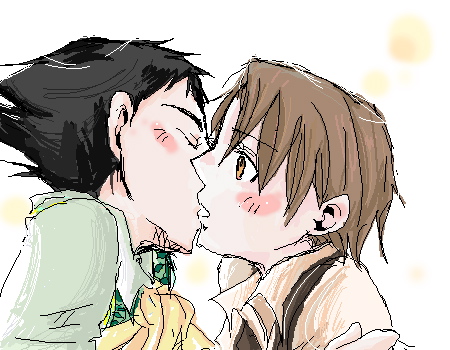
もちろん、シナリオにそんなシーンは、ない。
羊飼いに扮したミサキは唖然とした。が、ツバサはそのまま演技を続けようとしている。
このアクシデントに、観客たちは大喜び。大きな拍手が巻き起こった。
舞台袖のミスギたちも一瞬唖然としたが、その観客たちの様子を見て、皆で顔を見合わせてにんまりとした。
そうして大喝采の中、無事に劇は終了した。
「おい!ツバサ!お前、なんだかんだと俺達をビックリさせてくれるなー!」
「ミサキと、あんな秘密の打ち合わせしてたなんてなぁ。」
「僕も知らなかったんで、びっくりしたよ。でも、大ウケで良かったね。」
クラスメイトたちが次々にツバサに駆け寄り、肩を叩いた。
そんなクラスメイトたちの波をかき分け、ツバサはミサキの姿を探した。見当たらない。
やはり、怒ってしまったのだろうか…。
あのキスはもちろん、ミサキと打ち合わせしたものなんかではなかったのだ。
劇が終わるとミサキはロザリーの衣装のまま、温室まで走って来た。
温室は学校の裏手にあるので、創立祭で人が大勢いる時でも目につくことは、ない。
ミサキは寂しかったり辛かったり、混乱して心が平常心を失う時にはよくここへ来た。
どんな時でも黙って楚々としている花たちを見ると、だんだんと穏やかな心が戻ってくる気がするのだ。
「お前、嫌がってなかったろ?」
声に振り向くと、案の定、ゲンゾーが立っていた。
「嫌がるも何も…僕が騒いだりしたら、劇、めちゃくちゃになるだろ?せっかく皆で準備したのに。」
「…劇は無事終わったかもしれないがな、俺の気持ちはめちゃくちゃにされたぞ。」
ゲンゾーは特に表情を変えずに淡々と言ったが、明らかに心にある種の感情を抑えているようだった。
「…なんなの?その言い方。ゲンゾーらしくないよ?」
「……俺らしくない、か。ああ、悪かったよ。…お前、ツバサが好きなんだろ?」
ミサキは、カっと頭に血が昇るのを感じた。こんな感じは、初めてだった。
バチン!ミサキはゲンゾーの頬をぶった。
「なんだよ…!人の気も知らないで……!ゲンゾーの大馬鹿野郎!」
そう言い、またどこかへと走り去ってしまった。
「いってぇなぁ…。ほんとに、痛てぇ、よ…。」
ゲンゾーが頬を押さえて呟く。もちろん、痛いのは頬だけではなかった。
「わーるい、聞いちまった…。つまんねぇからこの裏のベンチで昼寝してたんだけどよ。」
「…コジローか…。」
「しかしよぉ、ほんとに、自信家のお前らしくないんじゃねぇのか?今の。」
コジローの言葉を聞いて、ゲンゾーは自嘲気味に笑った。
「…俺らしいよ、この上なく。……あいつ、もう、許してくれねぇかなあ。」
「だーいじょうぶだって。」
コジローはいつもより小さく見えるゲンゾーの肩を思いっきり叩いた。
「あいつがあんな顔するなんて、お前の前だけだろ?だから、大丈夫。」
「……なんか、よく分からん理論だな。」
ふと横に目をやると、ミサキが「なかなか咲いてくれないんだ」と言って丹念に世話をしていた、小さな可愛らしい薔薇が咲いていた。
「でも、ありがと、な。」
ちゃんと仲直りしろよな、と言い残し、コジローは去って行った。
「ミサキ、ごめん。」
温室を走り出てから、プラプラと講堂へ戻ろうとした時、ツバサに声を掛けられた。
ツバサもまた、オーランドの衣装のままだった。真剣な、思いつめたような目をしている。
「嘘つき。ツバサ、僕には指一本触れないって−−−自信があるって言ったじゃないか…!」
「ごめん。ミサキ、ごめん…。ミサキの顔を近くで見たら…」
ツバサは本当に申し訳なさそうに、深々と頭を下げた。
あれは、衝動的だったのだ。
ミサキの大きな瞳が自分の目をじっと捉え、その深い美しいブラウンに吸い込まれるようにキスをしていた。
直後、表情の固まっているミサキに気付いた時にはしまったと思ったが、もう遅かった。
しばらく頭を上げる気配のないツバサを見、ミサキは小さく溜息をついた。
「……もう、いいよ。終わったことだし。びっくりしたけど、怒ってはいないよ。」
そう言われてツバサは初めて頭を上げた。ミサキの表情は、いつものように微笑んでいた。
「けど、ゲンゾーが…。ごめん、さっき、聞こえちゃった…。」
「これは、僕とゲンゾーの問題だよ。君のせいじゃ、ない。」
ミサキにぴしゃりと言われ、彼が見た目に寄らず意外と頑固なことを知っているツバサは、それ以上口を挟むのを止めた。
「さ、ツバサ。早く戻って着替えよう。皆きっと困ってるよ。」
「あ、…うん…。」
温室の方を振り返ったツバサは、屋根に反射した光の眩しさに目を細めた。
next
>>To CHAPTER 3
|